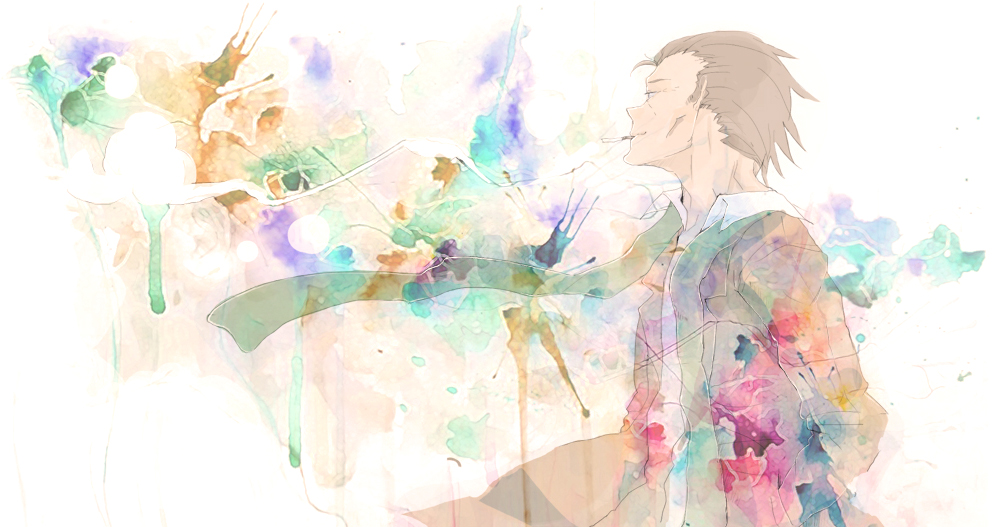僕は結構真剣だったんだ。
でも、真剣になる相手を間違えってしまったのかもしれない。
冷えすぎたコンビニの冷凍庫みたいに、イライラするくらい凍てついたベランダで僕は煙草をふかす。
目に映る風景は、何も語らない暗闇と、そこを漂う営みの光。けれども、僕の電脳にその光はまるで届いていないようだった。ただ、煙草の味から伝わる情事の記憶を、何度も反芻しては溜息が止まらないのだ。
彼は、誰よりも男らしく男で、とにかく夜の蝶のごとく自由に飛び回る。
そして何人もの人に愛の言葉を囁くのだろう。でも、そんなのは僕の行きすぎた妄想でしかないのかもしれない。
僕は確信したかった。彼は必ず僕のところに帰ってくると。例えどんなに飛び回ろうと、僕の隣で羽を休めているのだと。
週に何回会っているとか、何度僕に告白の言葉をかけたとか、女々しくも、そんなことばかりを考えて、大丈夫だきっと大丈夫と言い聞かせる。
でも脳裏に残る、彼の確信のない虚ろな行動の数々に僕の希望は空しくも打ち砕かれて粉々になりそうだった。
それほど高くもないベランダからは、街を彷徨う人の往来がぼんやりとだが見て取れる。
その中に彼の姿はないかと、探したくもないのに探してしまう。暗いブラウンのコートを着た細身の男性を見つけると、僕は一瞬だけ胸が高鳴り、そしてそれは、ほんの一小節も続くことはなく、また過去の記憶へと煙草の煙のごとく燻らせてしまう。
「パズ・・・」
思わず呟くその名前だって彼を表す記号のようなもので、本当の彼を語る力があるのか僕には分からなかった。
ただ、僕はいつだって彼の電脳に浸入し、彼の記憶や経歴、街での痕跡を辿ることができる。きっと、これは昔なら携帯電話をのぞき見るとか、上着のポケットをチェックするとか、そういうことであって、そんなことをしても、ただ僕が傷つくだけだって分かっているから、絶対にそれだけはしないようにしていた。
そんなことよりも、彼自身の、彼のゴーストが欲しい。
見下ろす外界は、よそよそしく僕を置いてけぼりするから、
夜の街を、適当なバスに乗りながら彷徨う時のように、僕は自分の意識を虚ろに飛ばすのだった。それは、ガラス越しに自分の顔を見つめながら、時に路端の見知らぬ人と目が合う時のような、そんな曖昧で無責任な心地。錯綜する風景の中で無理矢理自分自身を見いだすような空虚で真っ黒な無意識が、マグロのように僕の中に横たわる。絶え間なく点滅する、人を乗せた人工物が都市の明かりに溶け合う様は、何度見つめても僕の意識を麻薬のようにまどろますのだ。
「パズ・・」
オレンジや黄色のネオンが、窓ガラスにこびりついた都市の垢に反射し、時折赤いランプが溶けるように不規則に走る。
そんな日常の移ろいが何度も何度も僕のふたつのガラス玉に繰り返し映し出されていくうちに、
全くもって恐ろしく、気が狂う位に彼の温度を自分の電脳にこすり合わせてしまう。
「・・・寒い」
自分の肉体に自分の爪先を立てて、きりきりと痛む何かを感じながら、暗闇をじっと見つめていると、ふと、赤いランプの狭間から、すらりとした人影が、迷いなく颯爽と近づいてくるのを発見した。
コツコツと靴の音が聞こえてきそうな、軽やかで優雅な足取り。実際はどうなのだろうか。彼はそこいらの平凡な男と同じような足音と足取りなのだろうか。もう全然分からない。でも、僕の電脳はとうの昔に真っ黒に焼き切れてしまっているから、そう映し出されるのだろう。
「 」
「あんたが、煙草をふかしても、驚くほど様にならないな。」
僕が言葉を発する前に、彼の涼しげな声が耳管をぐらぐらと揺らす。
どんな顔をしてしまっているか分からない。彼のように綺麗な笑みを浮かべるべきなのか、それともポーカーフェイスを繕うべきか、それとも怒った鳥のように睨み返すべきなのか・・・
僕は自分の感情と義体を摺り合わせ、懸命に結論を導き出し、制御しようとしているのに、僕の身体は混乱を極めいうことをきかない。
こんなことなら感覚器官を切っておけばよかった。顔の皮膚組織がめくれ上がって落っこちていたかもしれない。
「早く、きなよ。」
僕は精一杯平静を装って、喉につっかかりそうな言葉を何とか吐いた。
彼は相変わらず涼しげに煙草をふかしながら、僕の方をじっとみつめている。見透かされているんだろうなと思いながら、僕は彼の視線から逃げだしたいのを抑え、じっと彼の視線に応えた。ああ、それだけでも上出来じゃないか、僕は。
「たまには、俺の家に来るか?」
ふっと細い煙糸を、その薄い唇で描きながら、彼は突拍子もない提案を吐いた。
彼の家になど今まで行ったことなんてないのに、あたかも行ったことがあるかのように言うその様子に、ちょっとイラっとする。いやかなり、イライラしてきた。
「面倒くさい。」
「ここまで迎えに来てやったんだ。つべこべ言うな。出てこい。」
僕はあの膨大ネットから、何度検索した分からない、女々しい恋のワードから導き出した、いくつかの無責任で身勝手な答えを思い出して、彼が初めて家に招く意味について心を躍らせながら考えていた。
僕の電脳は随分と生々しい程に人間臭くて、そしてそれを辞めさせてくれない強烈な恋の塊に、
僕は自分自身のゴーストの気配を、何度も何度も噛みしめずにはいられないのだ。
「分かった。ちょっと、待ってて。」
気の利いた台詞の一つも思いつかない僕の”ゴースト”と共に、僕は全身全霊が喜びと安堵に包まれるのを感じながら、温かな部屋へと戻り、クローゼットで暇にしていたお気に入りのダウンコートを引っ張り出す。
彼が目の前にいるだけで、馬鹿みたいに単純に動き出す自分自身を、僕はぎゅっと抱きしめずにはいられない。
『5分。それ以上経ったら帰るからな。』
電通で示された宣告は、あまりにも短くて、髪を梳かすどころか靴下を履く時間すらない程で、僕はコートを羽織り、ベランダにあった寒々しいサンダルをそのままに、玄関を飛び出した。