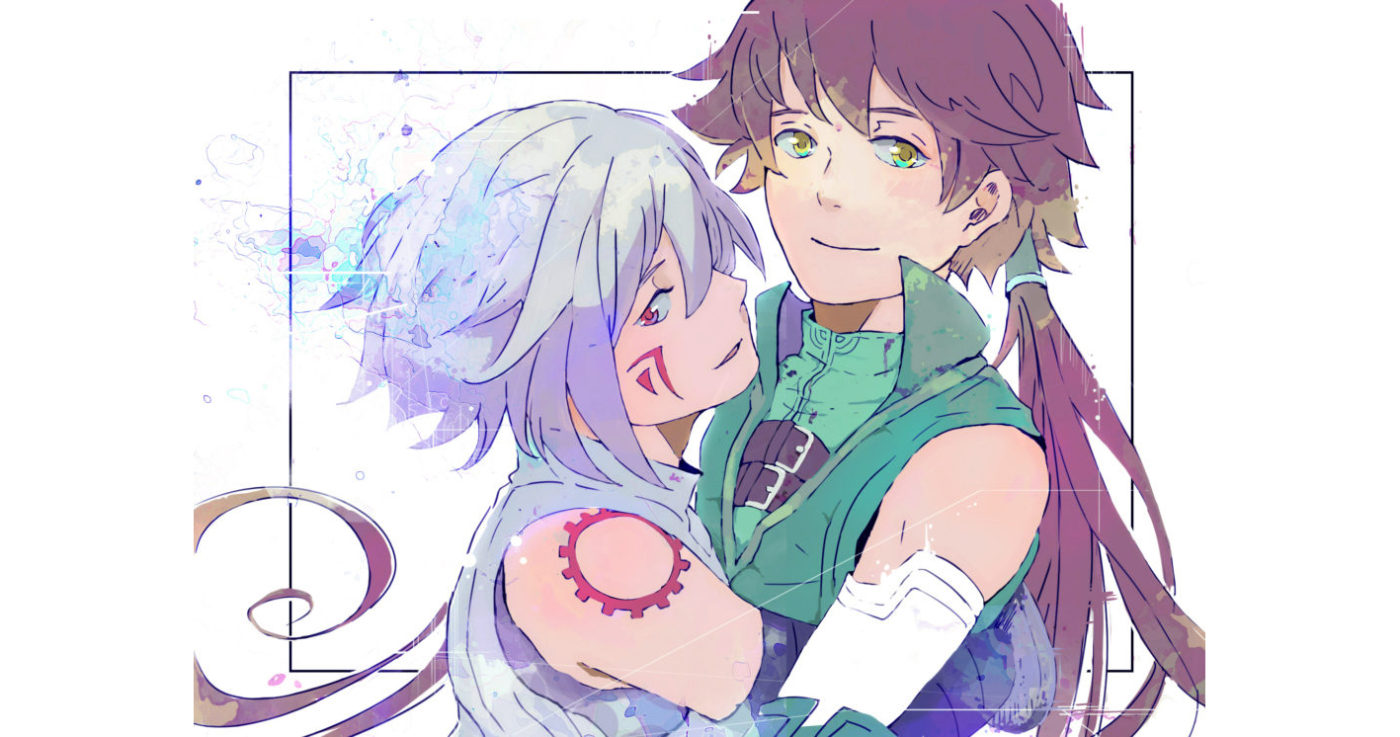1.
シラバスと、いわゆる恋人―――という形になってからというもの、今までとあまり変わりない日々が続いていた。一緒にいる時、以前より甘い雰囲気を感じることは増えた気もするが、時々本当に恋人なのか疑わしくなるくらい周囲の人間と変わりのない態度で接してくる。
シラバスは俺との関係性が変わろうとも、カナードの仕事をいつも通り優先的にこなしていたし、ガスパーや友人たちと一緒に行動することも多い。だからこそ最近少し物足りない。もう少しより深い関係に進みたい。できることなら抱き合ってみたい……と思っているが、なかなかそういった雰囲気になってくれない。だから今日こそは、無理やりでもいいから彼がその気になるような、断わり難い状況を作ってみようと考え、ここ、カナードの@Homeに意気込んでやってきたのだった。
「やぁハセヲ! 今日は時間あるの?」
@Homeに着くと、案の定いつもと変わらない調子でシラバスが話しかけてきた。意気込んで来たものの、これといって上手い作戦が思いついていたわけでもなく、俺はただじっとシラバスの顔を見つめてしまう。すると「どうしたの?」といったような能天気な顔で見つめ返してくるものだから、俺はそんな不用心な彼を困らせてみたくなって、唐突に噛みつくようなキスをお見舞いした。
「…え…っ! ……!!?」
あまりにも突飛な行動に、さすがのシラバスも驚いたようだ。なんとなく甘い雰囲気になった時に、ちょっと触れるか触れないかのキスを何回かしたくらいだったから。しかもここは@Homeのロビー。いつ誰が来てもおかしくない状況だ。
「…っん、んん…っ! ハ、ハセ……ヲ…!」
自分でも驚くほど強行突破な作戦だと思った。しかし意外とこれくらい強引な方が彼には効果的かもしれない。乱暴なキスにシラバスが必死に抵抗しているのが分かる。それでも離したくない。今日こそはもう逃がしたくない。
「ハセヲ! ここでは、だめだよ……!」
「やだ」
「で、でも! せめて…… 場所は変えないと……」
俺は一度唇を離してシラバスを見つめる。顔を真っ赤にさせて戸惑うシラバスが、自分の腕の中で身を縮こまらせているものだから、もっともっと困らせてみたくなる。
「じゃあ、こっち。来いよ」
俺はシラバスの手をひいて@Homeの工房に移動する。そしてすぐさまシラバスの身体を床に押し倒した。
「…ハ、ハセヲ……!?」
「俺さ。前からこういうこともしたかったんだ」
「…っ……」
「恋人、なら、いいだろ? ダメなのか?」
逃げられないようにシラバスの両脇に手をついてまっすぐ見下ろすと、彼の身体がきゅっと緊張したのが分かった。しかし殴るでも蹴るでもなく、この状況下にも関わらず頬を朱に染め、戸惑いの色を見せている。そんな様子を見せてくれるだけで彼と俺は一応恋仲なんだなと思えてきてほっとする。
「………ええと………………ダメじゃ、ないけど………でも……」
「いいんだな?」
彼の弱弱しく曖昧な返事に対して俺はすかさずハッキリと現実を突きつける。イエスかノーか。少なくとも俺は彼がノーという状態で先に進められるほど強靭な精神を持ち合わせてはいなかった。
「……えと、ハセヲが、したいなら………いい、けど……」
視線を俯きがちに彷徨わせながら、聞こえるか聞こえないかの小さな声で彼はそう言った。そう、間違いなくそう言った。いわゆる「イエス」と応えた彼は、今までに見たことないくらい恥ずかしそうな表情を浮かべていて、それを見ることができただけでも今日は大収穫だ。しかしこんなチャンスを放り投げて帰るほど、俺も愚かじゃない。俺はその言葉を合図に、シラバスの首筋にそっと唇を寄せた。
「……っ…! ハセヲ……!」
「今日は逃がさないからな……」
首筋から耳の後ろにかけての、唯一彼の素肌が露わになっているあたりに触れるか触れないかのキスをお見舞いする。それだけでぴくっと肌を震わせるものだから、この先続けたらどうなってしまうのだろうかと期待で胸が躍り出す。肌に唇を添わせると、甘くて優しい何かの花のようなとてもいい匂いが、温もりと共に浮かび上がってきて、俺は思わずうっとりとそれを吸い込んだ。
「シラバスの匂いがする……」
「……そんな……あんまり嗅がないでよ…………」
「……んー、でも、すげぇいい匂い」
抱きしめることで、ようやく知ることが出来た彼の匂い。
肌から控めに浮かび上がる素敵な匂いをもう一度胸いっぱいに満たしてから、彼の上着をゆっくりと脱がせていく。ちょうどいい感じに前開きの衣装だったから、とても脱がせやすい。俺は前をはだけさせ、露わになった白い肌にそっと唇を這わせた。
「……ぁ……やっぱり………待って………」
「待てねぇよ」
「…………っ……!」
上着の影で見え隠れしていた桃色の乳首をそっと舐めると、シラバスの身体がぴくりと跳ねる。そのまま飴玉を舐めるかのように舌先でちょろちょろと転がしながらその味や感触を堪能していく。
「……っ、ぁ……そんなとこ……」
「美味しい」
「……ば、か……っ…そんなわけ……」
確かに何か味がするというわけではなかったけれど、そのほのかな甘い香りと混ざり合ってとても素敵な気分だ。俺はふたつの乳首を交互にたっぷりと舌先で愛撫し、ぷっくりと紅くなるまでしっかり味わった。そうしている間に、上着はもちろん、腰のベルトやブーツ、ゆったりとしとたズボンなんかも着々と脱がせていく。上半身の至る所にキスを降り注ぎ、すっかり敏感な様子になってきた頃には、彼は無防備にも下着だけの姿になっていた。
「………ハセヲも、……脱いでよ……」
そういえば、肝心の自分はグローブを外した程度で、ベルトも装具も何一つとして脱いでいないままだった。目の前でほとんど裸になっている彼とは随分と対照的な状況だ。確かにとても柔らかそうな彼の身体を全身で抱きしめたい気持ちに駆られたが、今はとにかく、シラバスの色々な姿を見てみたくて、ひとまず彼の提案を無視した。俺は彼の下着の上から、その下ですでに大きくなり始めている性器をやんわりと愛撫する。すると本当に甘い声を漏らして恥ずかしそうな顔をするものだから堪らない。
「…ぅ、ぅ…ぁ……だ、め……」
気持ちよさそうな声を漏らしながら快感に流され始めた隙に、彼の下着を一気に引きずり下ろした。下着の中からぴくんと、張り詰めた性器が跳ねるように飛び出してきて、俺は思わず息を飲んだ。当たり前だが彼もちゃんと男だったんだな、と冷静に思いながら、その淫らな姿に興奮が高まってくる。
「……ぅ……ぁ…ハセヲ……っ……」
俺は彼の性器をしごきつつ、先走る白い液体を指に絡めて、後ろの窄まりに向かって這わせていく。
「……そこ、挿れるの……?」
「だめか?」
「……挿れ、たいの……?」
「…ああ」
彼の中まで触れてみたい。彼の誰にも見せたことない姿も、聞かせたことのない声も、なにもかもを感じたい。
「じゃ、お願いがあるんだけど……」
「なんだ?」
「ハセヲも、脱いで………」
全身を熟れさせながら、ささやかにそう懇願するシラバスの提案を一体誰が断れるというのだろうか。
「わかった。それだけで、いいのか?」
そう聞くと、彼はただ小さく頷いた。
2.
「……挿れる、ぞ……」
シラバスのおしりの隙間に隠れていた秘部を可能なかぎり丁寧にほぐしてから、俺は手探りでそこに性器をあてがった。ふたりきりで、人前で裸になったことなんてなかったからすごく緊張したし、すごく恥ずかしかったけれど、シラバスは俺の行為ひとつひとつをしっかりと受け入れてくれたので、恥ずかしい気持ちをなんとか乗り越えることができた。彼とはもちろんのこと、今までこうやって他人と繋がった経験はなかったから、頭の中が真っ白になってしまって、そんな俺に見かねてか、彼はかなり積極的に俺のことを導いてくれた。
「うん。ここに、そう、ゆっくり挿れて……」
「こ、こうか…?」
まるで戦闘のやり方を教える時みたいな口ぶりだから、初めてシラバスに出会ってサポートを受けた時のことを思い出す。今回は本当に初心者だったが……。実際にこうして教えられると何だかとても恥ずかしくなってくる。無理やり入れたらどんどん中へ入りそうな気もしたけど、俺はとにかく彼の言う通りに、何度も確認しながらゆっくり腰を進めた。
「痛くないか? 痛かったら……」
「ううん、大丈夫だよ」
仰向けの状態で恥ずかしそうに少しだけ足を開きながら、俺のことをそっと促してくれた。どんな時でもいつも優しく接してくれるから、初めて出会った時から警戒しないでいられた気がする。俺のことを全くと言っていいほど疑うことなくそこにいてくれる。今だって、そうしてくれるから、迷うことなく、ただひたすら彼を信じて行為ができる。
「シラバス……」
いつもはしっかりと着込んでいる衣装だったから、まさかこんな、素足やおしり、ましてや性器まで見せてくれるこの状況に、とてつもない眩暈を覚える。あまりにも強烈なビジュアルだったけど、目を離すことができない。たぶん俺はずっと、彼のこんな姿も見てみたかったんだ。誰にも見せないこんな姿も。
「……ハセヲ………」
俺は腰をゆっくり回すように進めながら、より深いところへと進んでいく。じわじわと擦れてそれだけでもすごく気持ち良くて、ああ彼の内側にいるんだな、今彼と繋がっているんだなということを実感し、とても満たされた気持ちになってくる。全身をぴくん、ぴくんと震わせながら、無防備な姿を晒してくれる彼を見ていると、どうしようもない興奮と衝動が迫ってきてしまう。
「……っ、ちょっと動くぞ……っ……」
「…ぅ、ぁ……待っ……っ……!」
もしかしたら動くのはまだ早かったかもしれないが、我慢できそうにない。俺は一度彼の足を抱え直し、目の前で濃密にとろけ始めているお互いの結び目を見つめながら腰を揺り動かす。ゆっくり馴染ませたかいがあってか意外と柔らかく、中はたっぷりと温かい。ずちゅ、ずちゅと濡れた音が鼓膜を揺さぶる。
「……っ、ハ、ハセヲ……まって……!」
慌てだすシラバスの様子を後目に、太ももをさらに大きく開かせて、咥えている場所を眺めながら腰をずんずんと打ちつけていく。すると突然、さっとそこを手のひらで隠してしまった。
「あ、おい、隠すなって!」
「…や、だ……そんな、見ないでよ…………」
俺はその手のひらを払いのけてぐっと腰を深める。しかし今度は足をぎゅっと閉じて抵抗してくる。恥ずかしいのは分かるけれど、抵抗されると行為がし辛い。俺は仕方なく足の間に割り込んでぐっと身体を引き寄せ、シラバスの顔を覗き込んだ。すると今度は顔を両手のひらで覆い隠してしまった。
「だから…! 隠すなって…!」
「だ、だって、そんなこと言ったって…………やっぱり、恥ずかしいよ……」
表情は見えなかったが、隠した指の隙間から覗く頬や目尻が真っ赤になっているものだから、その指を退かしたくて仕方なかった。しかしそんなことをしたら、本気で嫌がられそうな気がして、俺は仕方なく少しだけ身体を離してから律動を再開することにした。しかし彼は顔を背け、表情をすっかり髪の下に隠し、さらに性器のあたりを再び両手で覆い隠してしまう。
「…おま………」
「……ご、ごめん………」
「お前……なぁ、いい加減にしないと、縛るぞ……」
思わずそんなことを言ってしまう。
もちろんそんなことをする気はなかったし、シラバスが何から何まで隠したいというのであれば、ある程度は許容してあげたい気もした。しかし身体の奥底から、ふつふつと狂暴な衝動が押し寄せてきていて、とにかくシラバスの全身を余すことなく感じたい気持ちでいっぱいだった。それにお互いが身体を隠し合ってしまっては何のためにこんなことをしてるのかと、思えてこなくもない。もちろん、見えなくたって俺はもう十分にシラバスを感じてはいたけど。
「じゃ、じゃあ縛ってよ……無理だよ、こんな……っ………」
目の前で顔を真っ赤にしながら、絞り出すような声でそう言った。俺は一瞬耳を疑ったが、彼の様子を見る限り本当にそう言ったようだ。しかしそうであれば提案に乗らない手はない。
「本当に縛るからな……後悔しても、知らねぇぞ」
俺は工房の素材庫から手頃なロープを取り出し、シラバスの腕に絡め頭の上でしっかりと結ぶ。頭の上で両手を縛りあげられたシラバスを目の前にしたら、突然もの凄い背徳感を覚えてしまった。しかし当の本人は黙ってその状況を受け入れているようだから、たぶん、大丈夫だろう。確かにあちこち隠していたシラバスの腕がないだけで行為に集中できるし、何より彼の身体がよく見える。白くて艶やかで、しなやかな男の身体。そこに胡桃色の長い髪がしっとりと流れている。俺は髪の下に隠していた表情をちゃんと見てみたくて、そっとその髪をかき上げた。
「……っ、……」
そこには今までに見たことのない、熱く蕩け、熟れた果実のように匂い立つ大好きな人の顔があった。
俺はまるで香りに誘われるミツ蜂のように、その唇にキスをした。そして床に横たえていた彼の身体を起こし、背中が壁につくように座らせてから再び足を抱え直す。
「……お前のせいだからな」
俺はこの状況をできる限り仕方のないこと、自分が望んでやったわけではないとうことにしたくて、彼に罪をなすりつけた。俺はシラバスの白い太ももをぐいっと持ち上げ、腰を深めていく。しっかりと性器を咥えて、ぱんぱんに震えている秘部が目の前いっぱいに広がるその光景に、思わず息を飲んだ。お互いの体液でとろとろになったそこは、あまりにも卑猥なのに、更なる刺激を待っているように見える。
「……ぁ…あ、…っ……や…っ…」
ぐりぐりと腰を回すと、背中をのけぞらせながら甘い声を漏らして足先まで震わせているから、きっととても気持ちが良いに違いない。俺はより甘く、よりとろけるように、シラバスの欲望を高めることに集中する。
「…ぁ…っ…あ、あ……ハセヲ……!」
巻かれたロープがギシギシと軋みだす。
3.
腕をしっかりと縛られた時、僕は少しだけ後悔した。
でもこうでもしないと、僕は絶対に隠れたくなってしまうし、これくらいの状況にならないとこの行為の恥ずかしさに耐えられる自信がなかった。
ハセヲのことは大好きだったし、今までにも時々ハセヲと抱き合えたら素敵だろうなと想像することもあった。でも、それはあくまで、僕がハセヲを抱くという想像だったし、ここまで本格的なところまで鮮明に思い描いたことはなかった。
完全に欲情しているハセヲを前にした時、ああ、僕の方が彼に抱かれるのだなと覚悟した。でも、可能な限り余裕を持って彼に接することが年長者としての最後の抵抗のような気がして、全てが初めてだったハセヲを精いっぱい優しく誘導した。そこまでは良かったんだけれど、それ以上先の行為は理性でどうにかなるものじゃなくて、ハセヲの行為がより激しく、より本能的になるにつれ、恐怖にも似た緊張と全てを隠したくなるような恥ずかしさでいっぱいになった。僕の身体をめいっぱい開いて、うっとりと見下ろす彼の姿を見た時、もう僕はハセヲに何もかも見られて、喰われてしまうような気がした。僕はハセヲが大好きだから、このまま続けたらこの先どうなっちゃうか分からなくて、すごい恥ずかしいこともいっぱいしてしまいそうで怖かった。
「じゃあ縛ってよ……」
思わず口をついて出た言葉。
でも、無理やりにでも縛れば、それのせいにできるかもしれない。全部が僕のせいというわけじゃない。僕がどんなに淫らになっても、それは僕の意思じゃないという免罪符になるんじゃないかと思った。
「……お前のせいだからな」
でもハセヲはあくまで僕がそうしろと言ったんだぞ、といった様子で腕を縛った。そして再び足を抱え直して腰の動きを再開させるハセヲは、今までに見たことのない大人の男の顔をしていた。
ちょっと肌に触れるだけで、ちょっと唇に触れるだけで幸せだった。いつもと変わらない日々を一緒に過ごせるだけで本当に。でも確かに、時々身体の奥から否応なしにふつふつと沸き起こってくる欲望があった。これはもう仕方ないものだと分かっていたけど、ハセヲを好きになってから、その欲望がハセヲに向いてしまうことが多々あって、ハセヲのことを考えながら欲望を高めるとすぐに気持ちよくなる自分がいた。そんなことくらいわかっていたけど、実際に抱き合うと、こんなにも、こんなにも恥ずかしいなんて……
「…ぁ…っ…あ、あ……ハセヲ……!」
腕に巻かれたロープが僕を離してくれない。動こうとするたび皮膚に喰い込んで痛い。隠れることが出来なくて、頭の先から足の先まですっかりハセヲに曝け出してしまっていることに、もの凄い恥ずかしさが込み合げてくる。
「や、そん、な……見ないで…………」
「………………やだ……」
繋がった場所が擦れてじんじんと痺れている。その痺れからとろけるような甘さが身体を駆け巡り、全身がとても敏感になっていくのを感じた。ハセヲがあの強い眼差しで、僕のことを嘗め回すように見ている。全身に彼の視線が突き刺さる。こんな恥ずかしい姿を、大好きなハセヲに見られるなんて。それなのに、こんな、気持ちよくておかしくなりそうなんて……
「…ぁ、ハセヲ……ハセヲ……っ……!」
「気持ち…良さそうだな、お前………」
「……っ…ぁ…い、い…っ………」
ハセヲの指先が、僕の性器に絡んで優しく愛撫してくる。一緒に戦いながら何度も握った彼の手。力強く手を取る時も、不安げに触れてくるときも、恥ずかしそうに掴むときも、彼らしくて大好きだった。そんな手のひらが、指先が、僕のそんなところに愛おし気に触れてくる。僕はもうぐちゃぐちゃになりそうだ。
「……ぅ、ぁ…ハセ、ヲ…だ、め……」
「……ん、気持ちいいか?……」
しっとりとした眼差しが僕のことを捕らえて離さない。このままだと果ててしまう。お願いだから僕を見ないで。
「…や、見ないで……っ、ぁ……も、う…っ………」
「……いいぜ。いけよ」
愛おしい声が鼓膜を揺さぶると同時に、僕の頭の中は真っ白になった。
4.
恍惚とした様子のシラバスが、ひときわ甘く顔を歪ませると、愛撫していた指の隙間から勢いよく精を放った。それは俺の腹をねっとりと汚し、そして彼の腹も同様に汚した。ぴくんぴくんと脈打つ感触を指先に感じると、この上なく満たされた気持ちになる。彼が果てた瞬間、きゅうと強い締め付けを感じ、すっかりはちきれそうになっていた俺もそのままあっけなく果ててしまった。
「……ぅ…ぁ……っ……」
締め付けてくる内壁がとくん、とくんと脈打ち、彼に包み込まれていることを実感する。繋がり合ったまま、全身が溶けてひとつになってしまいそうだ。俺はとろとろした彼の中の感触が名残惜しくて、繋がったままの状態でシラバスの身体をぎゅっと抱きしめた。お互いの体液でべとべとだったけれど、それすらも気にならないくらい目の前の温度が愛おしくて仕方なかった。
「大丈夫か……?」
すっかり四肢の力が抜けたシラバスが少し疲れたようなぼんやりとした表情で項垂れている。
俺はなんだか心配になって、そんな彼の頬にそっと触れてみた。すると、表情がふんわりと綻び、優しく見つめ返してくれた。
「……ん、大丈夫、だよ」
「本当か……? 無理させたよな……」
思い返すと随分乱暴なことをしてしまった気がする。
俺は先ほど縛ったロープのことを思い出し、急いでそれを取り外す。手首は少し赤く腫れ、じんわりと血がにじんでいた。
「……ごめん。痛かったよな。もうこんなことしないから……本当に、ごめん……」
「……ううん、いいよ。僕も、次はちゃんとハセヲのこと………」
何かを言いかけたシラバスがゆっくりと俺の身体を抱きしめてくる。ぴったりと寄り添う肌からほんのりと甘いシラバスの匂いがして、それは汗と混ざって、さっきとはまた違った匂いになっていた。
「ね、今日、どうしよっか……この後……」
「え? あ、そうだな。今日、なんか予定あったんだっけ?」
「ううん。特にないからマク・アヌの見回りに行こうかなって思ったけど……」
「あー、なんか人に会うのだるいな」
「うん、僕もなんか…… たまには一緒にクエストでも行く?」
2人用のやつあった気がするんだよね、と腕の中でもぞもぞと提案するシラバス。
今まで当たり前のように一緒に過ごしてきたけれど、こんなに近くに、自分の腕の中に彼がいるということは初めてで、俺たちは少し特別な関係になってしまったんだということを痛感した。
「そうだな。たまには、クエスト行くか」
「うん。じゃあ、よろしくねハセヲ」
腕の中で笑う彼は、友達になれた頃と変わらない笑顔でそこにいる。恋人と友達の間をくるくると回るシラバスの姿に、この先ずっとドキドキしてしまうのだろうか。でも、どちらであっても俺は彼のことが大好きで、とても大切であるということに変わりはない。いつまでも一緒にいられるなら、それがどんな形であれ構わないんじゃないだろうか。
そんなことをぼんやりと考えながら、愛おしい温度をしっかりと抱きしめた。