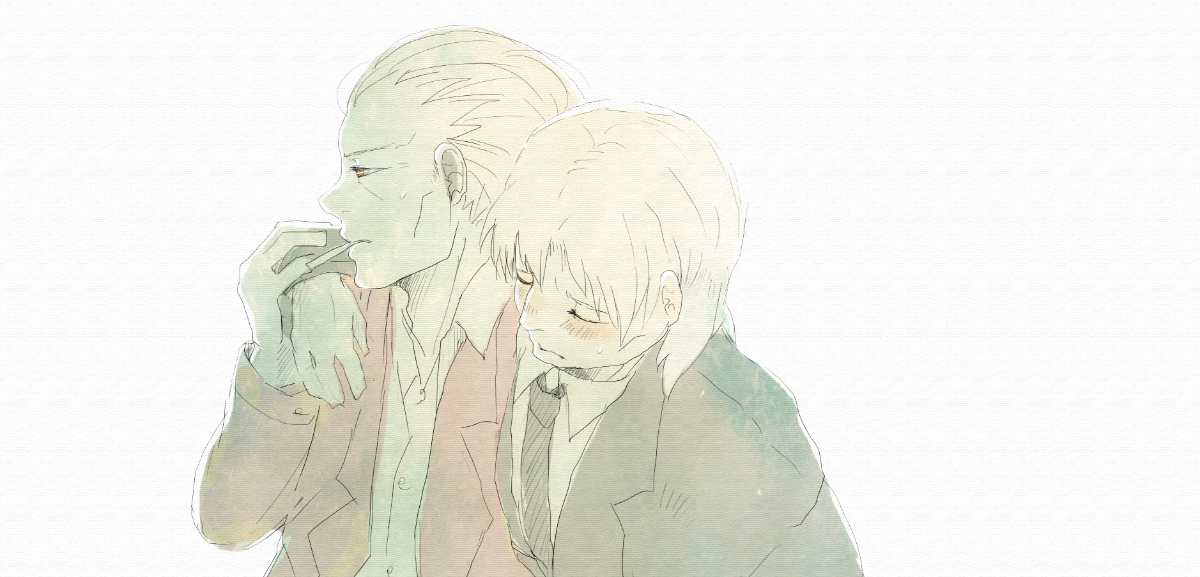酒臭い男を背負う趣味はないのだが、今夜はひと際酒臭い男が肩に乗っている。その男というのは会社の同僚であり、自分の上司であり、守るべき者でもある、公安9課の隊長トグサである。まだ週の半分も過ぎてないというのに、彼は非常に疲弊した様子で俺を飲みに誘った。
トグサが隊長に就任してから俺は彼の側近として、身辺警護からスケジュール管理までありとあらゆることに関わることになった。
今までは・・・少佐が去るまでは、飲みに行くどころか仕事以外で話すこともなかったというのに、ここ数ヶ月、毎日のように彼と時間を過ごすようになった。
「ごめん・・・いつもいつも・・」
トグサは、うめき声をあげながら律儀に何度も謝ってくる。
気にするなこれも仕事だ、と返しても、何度も同じ言葉で謝罪を述べてくるあたり、彼らしいと言えなくもない。
「タクシーが来るまでここにいろ。あとは自分で帰れるか?」
「う、う・・・うん」
曖昧な返事。この様子だと、家に辿り着く前に身ぐるみを剥がされてもおかしくない。さて、どうするかと考え倦ねていると、トグサが「なぁ。」と、蚊の鳴くような声を出した。
「なぁ・・・パズ、今日泊めてくれないか・・・その・・・」
こんな姿は、家族に見せたくないんだ・・・と、頼り無さげな声で呟いた。
「家族に見せられない姿を、俺に晒すのはいかがなものか?」
「パズは別にいいの」
少しでも時間があれば必ず家に帰るトグサにしては、非常に珍しい発言だ。なぜ彼がここまで酔いつぶれているのか、家に帰ろうとしないのか、大体の予想はついていた。
彼は、公安9課の隊長として、ひとつの決断をしたのだ。
「分かった。今日は俺のセーフを貸してやる。ただし、汚すなよ。」
寄りかかる身体から伝わってくる生身固有の温もりを感じながら、俺は彼が下した決断を少し呪った。
俺が彼に出来ることなんて、随分と小さなことだ。誰よりも近くにいる気がしてたし、誰よりも支えているような気でいたが、俺は彼が出す答えをただ聞き入れることしかできない。
彼の決断の対象になることもなければ、決断を変えることもできない。
「ありがとう。パズ」
感謝の言葉ひとつすら、どこか遠くに感じる。
彼は明日にでも家族に全てを打ち明けるだろう。
そして、その身体を手放すだろう。
今ここで感じている彼の肉体。血の音、汗の匂い、脈打つ温度。
どうしても、それを手放したくないと思ってしまっている自分がいる。
彼のゴーストは消えない。身体を手放しても消えない。そんなことは知っているのに、俺は、いつのまにか、トグサのありとあらゆる部分に執着していることに気がついた。
−−−今夜はあなたに全てを捧げます
確か、そんな酒言葉があったなと思い出しながら、
この若い隊長に、ゴーストを捧げ過ぎている自分を笑った。